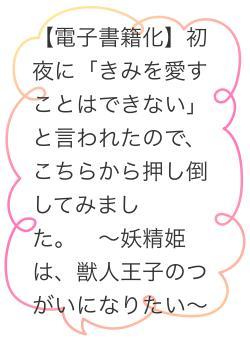【書籍化決定】身体だけの関係だったはずの騎士団長に、こっそり産んだ双子ごと愛されています
番外編 風邪には気をつけて
身体が熱くて、節々が痛い。寝返りを打つこともできないくらいに全身が怠いし、締めつけられるような頭痛もある。
ぼんやりと目を開けたライザは、力なく吐息を漏らした。
揃って風邪をひいた双子の看病をしていたら、今度はライザが体調を崩してしまったのだ。
高熱を出した双子たちは、それはそれは不機嫌で、常にどちらかが泣きじゃくっているような状況だった。
二人がまだ赤ちゃんだった頃を思い出すなぁ……なんて遠い目をしつつ、ライザはほとんど睡眠をとらないまま看病に明け暮れた。
間の悪いことに、イグナートは泊りがけの任務に出ていて不在だった。もちろん義父母やメイドたちも看病を手伝ってくれたのだが、体調の悪い双子はライザの姿が見えなくなるだけで号泣する。ライザが抱っこしていないと二人は落ち着いて眠ることすらできず、その結果見事に風邪をもらってしまったというわけだ。
双子はすっかり元気になったのだが、ライザは寝込んで三日目になる。子供からうつされる風邪は、どうしてこう治りが遅いんだろうと、ライザは自分の体力のなさをちょっと嘆いている。
「ライザ、起きたか。少し水分をとったほうがいい。そろそろ薬も飲まなきゃ」
すぐそばでイグナートの声がして、ライザは視線だけで彼の姿を探す。ベッドサイドに立つイグナートの姿を見つけて、ライザは返事をしようと口を開いた。だが、掠れた吐息が漏れるだけで、声が出ない。
「……ぇが、でな……ぃ」
「無理にしゃべらなくていい。少し身体を起こせるか?」
心配そうに眉尻を下げたイグナートが、ライザの身体をそっと抱き起こしてくれた。少し動くだけでめまいがするし、身体が重くてたまらない。自力で座っていられなくて、ライザはイグナートの胸に身体を預けた。
差し出された水を飲むと、ひんやりとしたものが全身に染み渡っていくようだ。水分をとったことで少し声が出るようになり、ライザは何度か咳払いをするとイグナートを見上げた。
「ごめんなさい、迷惑かけて」
「迷惑なんてこと、ない。俺のほうこそ、不在で申し訳なかった」
心配そうに頬を撫でる手が冷たい。きっとライザの身体が熱をもっているからなのだろう。
「子供たちは……どうしてる?」
「え……っと、それは」
ライザの問いに、イグナートは微かに視線を泳がせた。もしかしてまた風邪をぶり返したのだろうか。
一気に不安になったライザの頭の中を読んだように、イグナートは違うと言って首を振った。
「子供たちは元気にしてる。体調は問題ない。でも……」
「でも?」
「ライザに――ママに会いたいって言って、泣いてる」
ぼそりとそんなことを告げられて、ライザは小さく息をのんだ。
確かにライザが寝込んでからずっと、子供たちの顔を見ていない。イグナートや義父母に、双子の面倒は任せて療養に専念するようにと言われたし、ライザ自身も高熱で朦朧としていて子供の世話をするどころではなかった。
それでも、子供のことを忘れていたような罪悪感があって、ライザはうなだれた。
「私……自分のことばかりで」
「いや、熱にうなされながらも双子のことを気にしていた。俺が面倒を見ると言ったら安心したように笑ってまた眠ったが……覚えてないよな」
「そういえば、夢の中で二人の泣き声を聞いたような気がするけど……あれは本当に二人の声だったのかしら」
「やっぱりママが一番なんだよなぁ……。何度『おとーしゃんじゃ、いや! ママがいい』って言われたことか……」
そう言ってイグナートは苦笑する。だが双子を看病している間、アーラもパーヴェルも『おとーしゃん、どこ? いつかえってくる?』と、ライザに何度も確認していたのだ。それを伝えると、イグナートは嬉しそうに口元を緩ませた。
「私も、二人に会いたいな……」
「なんとか気を逸らそうと、今は二人にライザへのお見舞いの手紙を書かせてる。あとでそれを一緒に持ってきてもいいかな? なるべく接触は最低限にするから」
「うん。さすがに抱きしめるのは無理よね……。うぅ、早く二人を抱っこしたい。あのもちもちのほっぺに頬ずりしたい」
「俺がこうして抱きしめるだけじゃ、不満?」
悪戯っぽい口調でイグナートがそう言うので、ライザは思わず笑った。
「イグナートもあんまり近くにいると風邪がうつるわよ。心置きなく抱きあえるように、早く治すから」
「それって夜のお誘いかな」
「ち、違う……!」
「本当はもっと強く抱きしめたいし、キスだってしたいんだ。そうだ、風邪は誰かにうつすとよくなるっていうし、俺がライザの風邪をもらおうか」
「だめ……!」
本気でキスをするように顔を近づけられて、ライザは慌てて首を横に振るとイグナートの胸に手を当てた。彼はすぐに冗談だと笑ったが、ほんの少し残念そうな顔をしたような気がするのは見間違いじゃないと思う。
ただでさえ熱い身体なのに、更に熱が上がったような気がする。そんなライザを見ながら、イグナートは薬を差し出した。
「早くよくなって、ライザ。こうやって冗談を言いあえるくらい回復して安心したけど、ずっと心配だったんだ」
「うん、心配かけてごめんなさい」
「薬を飲んだら、また横になったほうがいい。あとで子供たちと一緒に様子を見に来るよ」
「分かったわ」
苦い粉薬を水で流し込むと、ライザは再びベッドへ横になった。
◇
目を閉じた瞬間に眠りに落ちたらしく、次に目を開けたら時計の針が随分と進んでいた。
薬が効いてきたのか、体の怠さは大分ましになってきている。
ゆっくりと身体を起こしたところで、部屋の外に人の気配がした。
「ママがまだ寝てるから、しーっ! だぞ。できるか?」
「できるよ!」
「だいじょぶ!」
「わぁっ、声が大きいっ! しーっ!」
こそこそと言っているつもりが、イグナートの声が一番大きい。ライザはくすくすと笑いながらドアの外に向かって声をかけた。
「起きてるから、大丈夫よ」
「ママ!」
ぴったり揃った双子の声と同時に、部屋のドアが開く。ぱぁっと目を輝かせたアーラとパーヴェルが、一目散にライザのもとに駆け寄ろうとして――ぴたりと足を止めた。きっと、ライザに近づいてはだめだと言い聞かされていたのだろう。
だけど、ライザだって二人の顔を見てこれ以上触れあわないなんて無理だ。子供たちからもらった風邪なのだし、再度うつすことはないだろうと判断して、両手を広げる。
「アーラ、パーヴェル。おいで」
「ママー!」
そんな声と共に、柔らかなぬくもりが二つ、腕の中に飛び込んでくる。子供たちの髪を撫でて、ライザは二人をしっかりと抱きしめた。
「ママ、もうだいじょぶ? なおった?」
パーヴェルに聞かれて、ライザは小さく首を振った。
「まだ、あと少しかな。でも大分元気になったから、もうすぐ治るわ」
「あのね、アーラね、おてがみかいたのよ。ママと、おとーしゃんのおかお、かいたの」
アーラは、握りしめていた小さな紙を差し出した。折り畳まれたそれを開けば、そこには可愛らしい絵が描かれていた。丸と点で描かれたそれは、似顔絵だ。
「すごい! 上手ね、アーラ。ありがとう」
「こっちがー、おとーしゃん。それで、こっちがママよ。ママは、まつげぱちぱちなの」
「ふふ、本当だ。ママは睫毛がついてて可愛い」
ライザが褒めると、アーラは得意げな顔をして笑った。それを見て、パーヴェルもポケットから紙を取り出す。
「ママ、パーヴェルもみて! これ!」
「うん、見せて、パーヴェル」
開いた紙には、アーラのものより力強い絵が描かれている。どうやら何かと戦っている様子を描いたものらしい。
「これは、なぁに?」
「これはねー、パーヴェルがわるものやっつけてるの! ママのおかぜさんも、あっちいけー!ってするよ」
「わぁ、すごい! パーヴェルがやっつけてくれたから、ママの風邪もよくなったのかもしれないわ」
「パーヴェルつよいもん!」
どうだと言わんばかりに胸を張るパーヴェルの頭を撫でて、ライザはイグナートを見上げた。
「子供たちを連れて来てくれて、ありがとう」
「うん。ライザもさっきより顔色がよくなってるな」
「もうピークは過ぎた気がするわ。怠さも大分ましになったみたい」
「よかった。でも、まだ無理は禁物だ。消耗してるだろうし、ゆっくり休んで」
そう言って、イグナートは子供たちにお見舞いは終了だと声をかける。だが双子はしっかりとライザに抱きついて動こうとしない。
「アーラ、ママとねんねするもん!」
「パーヴェルも!」
時刻はそろそろお昼寝の時間。眠たいのもあって、双子の機嫌はあまりよくない。ここで無理に離すと、きっと大泣きして大変なことになるのは目に見えている。
「ママはまだしんどいから、お昼寝はお父さんとしよう。な?」
「いーやっ! おとーしゃんと、ねんねしない!」
イグナートの言葉に、双子は同じ声でそう叫ぶとぷいっと顔を背けた。さすが双子、全く同じ顔で同じように頬をふくらませる様子は可愛らしくもあるが、イグナートはざっくりと傷ついた顔をしている。
ライザも双子を説得してみたのだが、二人はライザにしっかりと抱きついて離れなかった。寂しい思いをさせた自覚はあるので、ライザも無理に離すことをせず、一緒に眠ることにした。
両サイドからしっかりと抱きつかれて、ライザは二人の頭をそっと撫でた。満足げに笑った二人は、もう目がとろんとしてきている。
毛布をかけてくれながら、イグナートが眉尻を下げた。
「ごめん、しんどいのに」
「大丈夫。二人に癒されて、むしろ元気が湧いてきたわ」
「隣の部屋にいるから、何かあったら呼んで」
「うん、ありがとう」
体温を確かめるようにライザの額に手を押し当てたあと、イグナートは熱が下がっていることを嬉しそうに告げると部屋を出て行った。その背中を見送って、ライザはそっと目を閉じた。両隣から聞こえる小さな寝息に誘われて、あっという間に眠りに落ちる。次に目が覚めた時は、きっと全快しているような気がした。
その後すっかり元気になったライザは、『これで心置きなく抱きあえる』とイグナートにしっかり抱かれたのだが、それはまた別の話。
ぼんやりと目を開けたライザは、力なく吐息を漏らした。
揃って風邪をひいた双子の看病をしていたら、今度はライザが体調を崩してしまったのだ。
高熱を出した双子たちは、それはそれは不機嫌で、常にどちらかが泣きじゃくっているような状況だった。
二人がまだ赤ちゃんだった頃を思い出すなぁ……なんて遠い目をしつつ、ライザはほとんど睡眠をとらないまま看病に明け暮れた。
間の悪いことに、イグナートは泊りがけの任務に出ていて不在だった。もちろん義父母やメイドたちも看病を手伝ってくれたのだが、体調の悪い双子はライザの姿が見えなくなるだけで号泣する。ライザが抱っこしていないと二人は落ち着いて眠ることすらできず、その結果見事に風邪をもらってしまったというわけだ。
双子はすっかり元気になったのだが、ライザは寝込んで三日目になる。子供からうつされる風邪は、どうしてこう治りが遅いんだろうと、ライザは自分の体力のなさをちょっと嘆いている。
「ライザ、起きたか。少し水分をとったほうがいい。そろそろ薬も飲まなきゃ」
すぐそばでイグナートの声がして、ライザは視線だけで彼の姿を探す。ベッドサイドに立つイグナートの姿を見つけて、ライザは返事をしようと口を開いた。だが、掠れた吐息が漏れるだけで、声が出ない。
「……ぇが、でな……ぃ」
「無理にしゃべらなくていい。少し身体を起こせるか?」
心配そうに眉尻を下げたイグナートが、ライザの身体をそっと抱き起こしてくれた。少し動くだけでめまいがするし、身体が重くてたまらない。自力で座っていられなくて、ライザはイグナートの胸に身体を預けた。
差し出された水を飲むと、ひんやりとしたものが全身に染み渡っていくようだ。水分をとったことで少し声が出るようになり、ライザは何度か咳払いをするとイグナートを見上げた。
「ごめんなさい、迷惑かけて」
「迷惑なんてこと、ない。俺のほうこそ、不在で申し訳なかった」
心配そうに頬を撫でる手が冷たい。きっとライザの身体が熱をもっているからなのだろう。
「子供たちは……どうしてる?」
「え……っと、それは」
ライザの問いに、イグナートは微かに視線を泳がせた。もしかしてまた風邪をぶり返したのだろうか。
一気に不安になったライザの頭の中を読んだように、イグナートは違うと言って首を振った。
「子供たちは元気にしてる。体調は問題ない。でも……」
「でも?」
「ライザに――ママに会いたいって言って、泣いてる」
ぼそりとそんなことを告げられて、ライザは小さく息をのんだ。
確かにライザが寝込んでからずっと、子供たちの顔を見ていない。イグナートや義父母に、双子の面倒は任せて療養に専念するようにと言われたし、ライザ自身も高熱で朦朧としていて子供の世話をするどころではなかった。
それでも、子供のことを忘れていたような罪悪感があって、ライザはうなだれた。
「私……自分のことばかりで」
「いや、熱にうなされながらも双子のことを気にしていた。俺が面倒を見ると言ったら安心したように笑ってまた眠ったが……覚えてないよな」
「そういえば、夢の中で二人の泣き声を聞いたような気がするけど……あれは本当に二人の声だったのかしら」
「やっぱりママが一番なんだよなぁ……。何度『おとーしゃんじゃ、いや! ママがいい』って言われたことか……」
そう言ってイグナートは苦笑する。だが双子を看病している間、アーラもパーヴェルも『おとーしゃん、どこ? いつかえってくる?』と、ライザに何度も確認していたのだ。それを伝えると、イグナートは嬉しそうに口元を緩ませた。
「私も、二人に会いたいな……」
「なんとか気を逸らそうと、今は二人にライザへのお見舞いの手紙を書かせてる。あとでそれを一緒に持ってきてもいいかな? なるべく接触は最低限にするから」
「うん。さすがに抱きしめるのは無理よね……。うぅ、早く二人を抱っこしたい。あのもちもちのほっぺに頬ずりしたい」
「俺がこうして抱きしめるだけじゃ、不満?」
悪戯っぽい口調でイグナートがそう言うので、ライザは思わず笑った。
「イグナートもあんまり近くにいると風邪がうつるわよ。心置きなく抱きあえるように、早く治すから」
「それって夜のお誘いかな」
「ち、違う……!」
「本当はもっと強く抱きしめたいし、キスだってしたいんだ。そうだ、風邪は誰かにうつすとよくなるっていうし、俺がライザの風邪をもらおうか」
「だめ……!」
本気でキスをするように顔を近づけられて、ライザは慌てて首を横に振るとイグナートの胸に手を当てた。彼はすぐに冗談だと笑ったが、ほんの少し残念そうな顔をしたような気がするのは見間違いじゃないと思う。
ただでさえ熱い身体なのに、更に熱が上がったような気がする。そんなライザを見ながら、イグナートは薬を差し出した。
「早くよくなって、ライザ。こうやって冗談を言いあえるくらい回復して安心したけど、ずっと心配だったんだ」
「うん、心配かけてごめんなさい」
「薬を飲んだら、また横になったほうがいい。あとで子供たちと一緒に様子を見に来るよ」
「分かったわ」
苦い粉薬を水で流し込むと、ライザは再びベッドへ横になった。
◇
目を閉じた瞬間に眠りに落ちたらしく、次に目を開けたら時計の針が随分と進んでいた。
薬が効いてきたのか、体の怠さは大分ましになってきている。
ゆっくりと身体を起こしたところで、部屋の外に人の気配がした。
「ママがまだ寝てるから、しーっ! だぞ。できるか?」
「できるよ!」
「だいじょぶ!」
「わぁっ、声が大きいっ! しーっ!」
こそこそと言っているつもりが、イグナートの声が一番大きい。ライザはくすくすと笑いながらドアの外に向かって声をかけた。
「起きてるから、大丈夫よ」
「ママ!」
ぴったり揃った双子の声と同時に、部屋のドアが開く。ぱぁっと目を輝かせたアーラとパーヴェルが、一目散にライザのもとに駆け寄ろうとして――ぴたりと足を止めた。きっと、ライザに近づいてはだめだと言い聞かされていたのだろう。
だけど、ライザだって二人の顔を見てこれ以上触れあわないなんて無理だ。子供たちからもらった風邪なのだし、再度うつすことはないだろうと判断して、両手を広げる。
「アーラ、パーヴェル。おいで」
「ママー!」
そんな声と共に、柔らかなぬくもりが二つ、腕の中に飛び込んでくる。子供たちの髪を撫でて、ライザは二人をしっかりと抱きしめた。
「ママ、もうだいじょぶ? なおった?」
パーヴェルに聞かれて、ライザは小さく首を振った。
「まだ、あと少しかな。でも大分元気になったから、もうすぐ治るわ」
「あのね、アーラね、おてがみかいたのよ。ママと、おとーしゃんのおかお、かいたの」
アーラは、握りしめていた小さな紙を差し出した。折り畳まれたそれを開けば、そこには可愛らしい絵が描かれていた。丸と点で描かれたそれは、似顔絵だ。
「すごい! 上手ね、アーラ。ありがとう」
「こっちがー、おとーしゃん。それで、こっちがママよ。ママは、まつげぱちぱちなの」
「ふふ、本当だ。ママは睫毛がついてて可愛い」
ライザが褒めると、アーラは得意げな顔をして笑った。それを見て、パーヴェルもポケットから紙を取り出す。
「ママ、パーヴェルもみて! これ!」
「うん、見せて、パーヴェル」
開いた紙には、アーラのものより力強い絵が描かれている。どうやら何かと戦っている様子を描いたものらしい。
「これは、なぁに?」
「これはねー、パーヴェルがわるものやっつけてるの! ママのおかぜさんも、あっちいけー!ってするよ」
「わぁ、すごい! パーヴェルがやっつけてくれたから、ママの風邪もよくなったのかもしれないわ」
「パーヴェルつよいもん!」
どうだと言わんばかりに胸を張るパーヴェルの頭を撫でて、ライザはイグナートを見上げた。
「子供たちを連れて来てくれて、ありがとう」
「うん。ライザもさっきより顔色がよくなってるな」
「もうピークは過ぎた気がするわ。怠さも大分ましになったみたい」
「よかった。でも、まだ無理は禁物だ。消耗してるだろうし、ゆっくり休んで」
そう言って、イグナートは子供たちにお見舞いは終了だと声をかける。だが双子はしっかりとライザに抱きついて動こうとしない。
「アーラ、ママとねんねするもん!」
「パーヴェルも!」
時刻はそろそろお昼寝の時間。眠たいのもあって、双子の機嫌はあまりよくない。ここで無理に離すと、きっと大泣きして大変なことになるのは目に見えている。
「ママはまだしんどいから、お昼寝はお父さんとしよう。な?」
「いーやっ! おとーしゃんと、ねんねしない!」
イグナートの言葉に、双子は同じ声でそう叫ぶとぷいっと顔を背けた。さすが双子、全く同じ顔で同じように頬をふくらませる様子は可愛らしくもあるが、イグナートはざっくりと傷ついた顔をしている。
ライザも双子を説得してみたのだが、二人はライザにしっかりと抱きついて離れなかった。寂しい思いをさせた自覚はあるので、ライザも無理に離すことをせず、一緒に眠ることにした。
両サイドからしっかりと抱きつかれて、ライザは二人の頭をそっと撫でた。満足げに笑った二人は、もう目がとろんとしてきている。
毛布をかけてくれながら、イグナートが眉尻を下げた。
「ごめん、しんどいのに」
「大丈夫。二人に癒されて、むしろ元気が湧いてきたわ」
「隣の部屋にいるから、何かあったら呼んで」
「うん、ありがとう」
体温を確かめるようにライザの額に手を押し当てたあと、イグナートは熱が下がっていることを嬉しそうに告げると部屋を出て行った。その背中を見送って、ライザはそっと目を閉じた。両隣から聞こえる小さな寝息に誘われて、あっという間に眠りに落ちる。次に目が覚めた時は、きっと全快しているような気がした。
その後すっかり元気になったライザは、『これで心置きなく抱きあえる』とイグナートにしっかり抱かれたのだが、それはまた別の話。