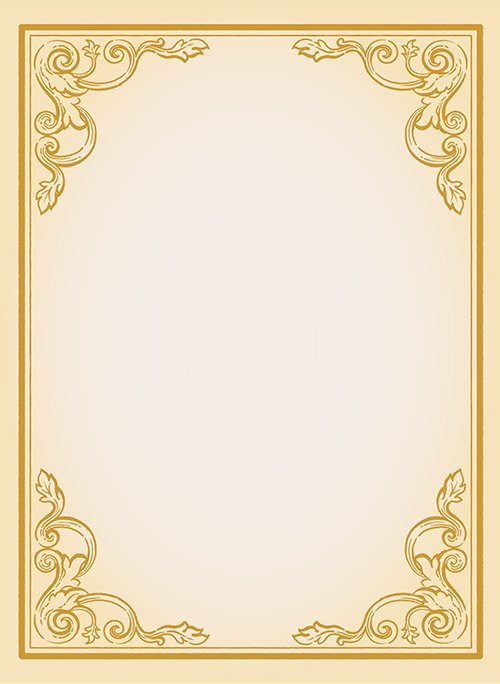無表情で心の壁がある婚約者様の感情が、絵で視えるようになりました。想像以上に溺愛されていて困惑しています。
ある日、無表情な婚約者様の感情が、視えるようになりました
しとしとと、霧雨が降り続き、冷たい空気が頬を撫でる、晩秋の真昼。
鈍色の空と堅牢な石畳が織りなす色彩の乏しい景色の中を、一台の馬車が走り抜けて、アデレイド王国の王都にあるブランシャール伯爵家のタウン・ハウスの前で停まった。
馬車の中から出てきたのは、亜麻色の髪を頭の後ろで結わえ、沈鬱な気配を漂わせる水色の瞳を黒いレースで隠した、二十歳の女性。
身に纏うドレスも、靴も、全て宵闇のような黒色だ。
その女性――伯爵令嬢のラシェル・マリュスは、二日ほど前に婚約者のロイク・ブランシャールを喪った報せを聞いたばかりだった。
二カ月前に視察のためここを発った彼は、乗っていた船が大嵐と魔獣の襲撃に遭い、帰らぬ人となった。
後に同じ航路を進んでいた船の乗組員が船の残骸から彼の遺体や遺品を見つけて、王都まで届けてくれたのだ。
タウン・ハウスの扉の前に立っている、初老と思わしき貴婦人が、傘を差してラシェルに歩み寄る。
艶やかな漆黒の黒髪を結い上げた、灰色の瞳をそっと伏せたその貴婦人は、ロイクの母――ブランシャール伯爵夫人。
ブランシャール伯爵夫人は、ラシェルの肩に優しく手をかける。
「雨の中、来てくれてありがとう。急に呼び出して、ごめんなさいね」
「いえ、ブランシャール伯爵夫人に会いたいと思っていましたので、とても嬉しいです」
大切な人を失ったもの同士で一緒に居た方が、ふとした時に感じる会話や表情の温度差に傷つかずに済む。
特に、ロイクの喪失をようやく受け入れ始めた今のラシェルの心は脆くて傷つきやすいため、同じ感情を抱いている者と一緒に静かに過ごしたかった。
「さあ、冷える前に中に入りましょう」
「はい」
ラシェルはブランシャール伯爵夫人に続いて、屋敷の中に入った。
二階へと続く階段の途中に、ブランシャール伯爵家の肖像画が飾られている。
ラシェルは足を止めて、肖像画に描かれたロイクを見つめる。
(もう、会えないなんて……)
ロイクはブランシャール伯爵の次期当主だった。
年齢は二十三歳。容姿端麗で、黒壇のような艶やかな長い黒髪をいつもきっちりと結わえており、切れ長の目は緑色。
顔が整い過ぎているため、一見すると冷たい印象を受ける。そして、寡黙で淡々と話すため一層、冷たく感じられる人だ。
しかし、一緒に過ごしている時にさり気ない優しさが垣間見えるので、ラシェルは彼を好きになった。
(たぶん、私の片想いで終わったのだけど……)
ロイクは優しいが、彼と話していると、自分たちの間に壁があるような気がしてならなかった。
だから、ラシェルはロイクに、お互いを愛称で呼び合うことや、敬語を取り払って話すことなどを提案し、親しくなるきっかけを作った。
ロイクは提案に乗って実践してくれたが、 それでもやはり、彼との間に壁を感じるのだった。
親同士が決めた政略結婚でも恋人のようになれないだろうかと夢見ていたラシェルにとって、彼とはあまり上手くいっていなかった。
(だけど、最期まで私を気遣ってくれていた)
ラシェルがロイクの訃報を聞いた時、懐中時計とその時計にまつわる話を書いた手紙を渡された。
ロイクの遺品を受け取ったブランシャール伯爵夫妻が、これらがロイクからラシェルにあてたものだと知って、ラシェルに手渡してくれたのだ。
懐中時計は、精緻な植物の模様が描かれた金色の本体に、水色の宝石があしらわれている。
ロイクが大切に保管してくれていたからなのか、正確に時を刻んでいる。
手紙によると、この海中時計は途中で立ち寄った港町の蚤の市で見つけた骨董品だ。
魔道具師が〝時戻り〟の魔法を付与した懐中時計らしいのだが、魔法の発動条件を知らせないままこの世を去ったから、誰も使えないらしい。
魔道具に興味があるラシェルのために購入してくれたのだ。
この世界では、誰もが魔法を使うことができるが、時間を操る魔法が使える者は一人もいない。
今までに幾人もの魔法研究者たちが研究をしてきたが、そのような魔法は完成していないのだ。
そのため、人間の持つ力では時間を操ることができないと言われている。
そのような背景もあり、眉唾物な懐中時計だが、ラシェルは肌身離さず持っている。
今も、ドレスのポケットの中に入れて持ち歩いているのだ。
「あの子の遺品を整理していたら、日記が出てきたの。勝手に見るのは悪いと思っていたのだけど、あの子の思い出に浸りたくて読んでみたら、あなたのことがたくさん書いてあって……あなたに知ってもらいたかったのよ」
ロイクの部屋に辿り着くと、ブランシャール伯爵夫人は一冊の日記帳をラシェルに手渡した。
ラシェルは日記帳の表紙を開くと、ぱらり、ぱらりとページを捲っていく。
『今日から、ラシェルをラシェと呼ばせてもらうことになった。ラシェは私を、ロイと呼んでくれる。
ラシェが私をロイと呼んでくれて、とても嬉しかった。ますますラシェを愛おしく思う。』
『ラシェとの会話では敬語を使わないことになった。
うっかり敬語で話してしまった私を見て、笑ってくれたラシェが可愛くて、見惚れていた。』
『外出先で見かけた花がラシェの好きな花だったから、ラシェの顔が思い浮かんだ。
近くの花屋で買って贈ろうとしたが、花屋には売っていなかった。
ラシェに会う口実がなくて残念だ。』
『視察で一人、他国に行くことにした。ラシェが知ったら、どう思うだろうか。』
ラシェルと会った日も、ラシェルと会わなかった日も、ロイクはラシェルについて記していた。
片想いではなかったのだ。
ロイクの心の中には常に、ラシェルがいた。
(ロイは……私を、愛してくれていたのね……)
愛を囁いてくれたことがなかったわけではない。
しかし、ロイクが無表情のままで伝えるものだから、本心なのか測りかねていた。
(もしも時間を巻き戻せるなら――旅立つ前に戻って、引き留めたい)
カチッと、時計の針が動く音がした。
ラシェルは辺りを見回す。壁にかけられている時計に目を留めて、あの時計から聞こえたのかもしれないと思い、視線を日記に戻した。
(ロイに、愛していると伝えたい)
カチッ、カチッ……。
絶え間なく聞こえる音が、次第に大きくなる。
その音が、壁に掛かっている時計よりも近くから聞こえると思ったラシェルは、ドレスのポケットから懐中時計を取り出すと、目を見開いた。
「懐中時計が……光っている……?」
なんと、懐中時計の内側から眩い光が迸ったのだ。
部屋中が照らされて、白く塗りつぶされる。
ラシェルは眩しさに耐えられず、思わず目を瞑った。
◇◇◇
眩しさが収まり、そっと目を見開いたラシェルの目の前に、足首まである長い白銀の髪と紫色の瞳を持つ、ラシェルと同い年くらいの美しい女性がいた。
女性と視線が合うと、女性は安堵したような笑みを浮かべる。
『おお、人の子よ、目を覚ましたか』
「あなたは……?」
『我は時の女神セレストの一部で、その懐中時計に宿っていた。おぬしとおぬしの婚約者の強い思いが合わさって、おぬしを私のもとに導いたのだ』
「時の女神……の一部? なぜ、一部なのですか?」
あまりにも不思議な表現だったため、ラシェルは目を瞬かせた。
『我はセレストが好奇心で分けた魂の一部で、人の子の生活を垣間見たいがために腕の良い魔道具師に頼んで、我の魂の欠片をその懐中時計のなかにおさめてもらったのだ』
「そんなことがあったのですね。ところで、どうして人間の生活を垣間見たかったのですか?」
『そりゃあ、人の子は観ていて面白いからだよ。特に、人の子の恋を眺めるのが好きで、この懐中時計を通して人の子たちの恋を見守れると期待していたのだが、〝時戻り〟の魔法を付与した懐中時計なんて宣伝文句をつけたせいで、力に固執したつまらない人間の手にばかり渡って辟易していたのさ。そこに、おぬしの婚約者が現れて、おぬしの手に渡ったのだよ。ようやく期待していたものを見られると思ったのに、まさかあのようなことが起こるとは……実に不運だった』
セレストは目を伏せた。
懐中時計の中から見たロイクの最期を思い出したようで、声は沈み、少し震えている。
『おぬしたちがお互いに想い合う様子に我の心は揺り動かされたから、一度だけ過去に戻ってやり直しの機会をあげよう。一度しか戻してあげられないから、後悔しないようにするのだぞ?』
「いいのですか?」
『ああ、その代わり、ラブラブな様子を見せつけてくれ』
「ラブラブ……になるといいのですが……自信がないです。それに、ロイはきっと、無表情ですし、私に遠慮しているところがありますし……」
ロイクは初めて出会った頃――十年前からずっと、感情表現が乏しい。
どうにか笑わせようとしてみたが、いつも失敗に終わったのだ。
『ふむ……それでは、恋人のためにこの懐中時計を購入し、自分の身を挺して贈り物を守っていたロイクのいじらしさに感激していたから、おまけをあげよう。ラシェルはロイクの本心が分からなくて困っていたようだから、ロイクの感情が分かるようにする』
「それは、どのようにわかるのでしょうか?」
『なに、すぐにわかるようになるさ』
セレストに聞いてみたところで雑な答えだけ帰ってきた。
そこをもう少し、とラシェルは言いかけたのだが、辺りはまた眩しくなり、白い光に包まれて、なにも見えなくなった。
◇◇◇
意識が浮上したラシェルは、ハッと目を見張った。
いつの間にか、自分の部屋――マリュス伯爵家のタウン・ハウスに戻っていたのだ。
カサリと紙の音がして、手に持っていた新聞を取り落としてしまったことに気づく。
拾って新聞の日付を見ると、二カ月前の日付が書かれていた。
「まって、ロイと最後に言葉を交わした日だわ……」
鏡を見遣ると、ロイクと会うために身だしなみを整えた自分の姿が映っている。
ロイクの瞳の色を意識した、緑色の上品なドレスを着ている。
髪はメイドに編み込みを入れてもらったハーフアップにしている。
「お嬢様、ブランシャール伯爵家のご令息がお見えになりました」
部屋に入ってきたメイドが教えてくれる。
ラシェルはロイクの居場所を聞く前に部屋を飛び出した。
(ロイクは庭園にいるわ。前はなぜ庭園に居るのだろうと思っていたけれど、私が好きな花が咲いていたからかもしれないわね)
日記を読んだからわかる。ロイクはラシェルが喜びそうなことを考えてくれていたのだ。
今からロイクと再会できるのだと思うと、心臓がとくとくと駆け足になる。
再会の感激に視界がじんわりと滲んだ。
ラシェルが目元に力を入れて止めようとしても涙が溢れてしまい、つうっと頬を伝った。
「ロイ! 待っていたわ――」
庭先に出たラシェルは指先で涙を拭い、ロイクを見た。
その時、目の前に現れた、ありえないものを見て目を瞬かせる。
「え……?」
視界の端に、落書きのような何か――絵文字の顔のようなものが現れたのだ。
その顔文字は、目を大きく見開いて【驚いている】顔だった。
目線を動かしてみたが、絵文字の顔はついてこない。それは、ロイクの顔の横にふわんと浮いている。
「ラシェ? どうかした?」
「ロイク、あの……顔の横になにかいるわよ?」
「顔の横に……?」
ロイクは絵文字の顔がある方向に顔を向けたが、すぐにラシェルに向き直った。
「虫……がいたのか? なにも見えなかったから、どこかへ行ったのだろう」
「そ、そう……なのね……」
そんなはずはない。今も自分の目には、見えるのだ。
(もしかして、セレストが言っていた、〝ロイクの感情が分かるようにする〟とは、こういうことなの?)
どうやら自分にしか見えないのかもしれないと悟ったラシェルは、それ以上のことは言わなかった。
今は、ロイクを引き留めることに専念しなければならない。
「泣いていたが……辛いことがあったのか?」
「い、いえ、これは……」
再会できた嬉し涙だと伝えようとして、口ごもる。
そのような事を言っても、信じてもらえないかもしれない。
もしも自分がロイクの立場なら、信じられないような話だ。
「……ロイクが船旅に出ることが、とても恐ろしいの。だから、今度の視察、絶対に行かないで!」
「……!」
ロイクが息をのんだ気配がした。
ラシェルがちらとロイクの顔の横を見ると、ふわんと浮かんでいる絵文字は目を大きく見開いている。
おそらく、【驚いている】顔だ。
「我儘をいっているのはわかっているわ。ロイが投資している商会との重要な視察だとわかっているけど、船旅でもしものことがあったらと思うと、怖くて……。ロイを失いたくないの」
ラシェルの声が震える。
今までロイクにここまで我儘や本心を伝えたことはなかった。
そのことを、今になって気づかされる。
「大好きなロイが死んでしまったら、どうしたらいいかわからないもの!」
「ラシェ……」
ロイクの顔の隣にある絵文字がくるくると表情を変えるため、気になってしまう。
絵文字は頬が赤くなったかと思えば、瞬時に変わって、にこにことした顔でハートマークを浮かばせている。
(ええと……頬が赤くなるのは、きっと【照れている】ということよね。ハートマークを浮かばせているのは、……【好き】ということ?)
ラシェルは戸惑った。
目の前にいるロイクの顔は、いつも通りの無表情なのだ。
それに、ロイクは自分の名前しか言わなかったのに、ここまで感情が変化するのか疑問だ。
絵文字が本当に彼の気持ちを表しているのか、わからない。
「ラシェがそこまで思ってくれていたのなら、私は視察に参加しない。もともと、一年後に控えているラシェとの結婚式の準備に時間を充てたかったから、断ろうか迷っていたところだった」
「えっ、いいの?!」
「視察に行かなくても魔道具で現地の映像を見せてもらえるから、構わない。結婚式は、ラシェとの一生に一度の思い出だから、できる限り一緒に準備をしたい」
ロイクの顔の横にある絵文字が、キッスを飛ばしている顔になった。
(え? この顔って……まさか、【愛している】?)
ラシェルは内心狼狽えながらも、平静を装う。
ロイクの顔と絵文字が一致しないが、話す内容とは一致するように思うと、急に照れくさくなった。
「結婚式のこと、そんなにも気にかけてくれていたのね……」
「ラシェとの行事なのだから、なによりも先に考えている。愛する人と過ごす時間の方が、何倍も大切だ」
ラシェルはロイクの顔の横をちらりと見る。
今度は、両目がハートになっていた。
(ええと……ハートがあるから……これも、【愛している】という意味?)
愛おしく思う感情の中にもレパートリーがあるようだ。
ロイクの顔はやはり無表情なので、ギャップに驚かされるばかりだ。
(言葉と絵文字は、一致しているのね。ロイクは大切に想ってくれていたのに、信じられなくて申し訳ないわ……)
それに、なによりもラシェルのことを一番に考えてくれているロイクのことが、愛おしくてならなかった。
ラシェルはロイクに抱きつく。
ロイクはぴくりと体を揺らしたが、ゆっくりと、ぎこちないながらもラシェルを労わるように、ラシェルを優しく抱きしめ返した。
「ごめんなさい。私、ロイの表情にばかり気をとられて、こんなにも大切に想ってくれていることにきづいていなかった」
「……ラシェは悪くない。私がラシェの立場なら、感情のこもっていない声と顔で何を言われても信じられなかっただろう。だから変わろうとしたのだが、幼い頃からの癖が抜けてくれなかった」
ロイクは初めて、彼が感情表現に乏しい理由を教えてくれた。
ロイクはラシェルに会う二年前、懐いていた剣術の先生に誘拐されたことがあった。
幸にも使用人がすぐに気づき、ブランシャール伯爵夫妻やブランシャール伯爵家の私設騎士団の騎士たちに伝えてくれたおかげですぐに助け出された。
しかし、信じていた相手からの裏切りに、ロイクの心はひどく傷ついた。
そんなロイクに、当時生きていた祖父が、「隙があるとすぐに狙われるから、感情を隠しなさい」と助言したのだ。
それ以来、ロイクは感情を上手く消すようになったが、逆に感情を表に出すことができなくなってしまった。
ラシェルは、感情を消そうとするほど傷ついたロイクに同情した。
「ラシェルをたまらなく愛しているのは本当なんだ。行動で示すと、伝わるだろうか?」
「たぶん……そうだとおもうわ」
ラシェルはそっと、ロイクの顔の横を盗み見る。
絵文字はまた、ラシェルにキッスする顔になっていた。
「本当は結婚式まで我慢していたのだが、ラシェに気持ちをわかってもらうためにも、我慢を止めよう」
「えっ、我慢って――んっ」
ロイクはラシェルの頬に手を添えると、唇をそっと塞いできた。
ふにゅと唇に触れた柔らかな熱が、ラシェルの唇に移る。
『ああ、よかった。めでたし、めでたし』
ラシェルは、どこからともなくセレストの声が聞こえてきたような気がした。
その後、ラシェルはロイクに訴えかけて、彼の投資先の人たちが嵐に遭わない日に出発することに成功した。
おかげで、その商談は被害に遭わず、今も健在だ。
ラシェルとロイクは二人で結婚式の準備をして過ごし、結婚後も仲睦まじく過ごした。
ロイクは言葉や行動でラシェルへの愛を伝えようとすることになったため、ラシェルは毎日ロイクにたくさん愛されて、最初は戸惑っていたが次第に慣れてしまう。
そうして一緒に過ごしていると、ロイクの顔の横にあった絵文字は、ある日突然消えてしまった。
しかし、その顔文字が無くても、ラシェルはロイクの気持ちが分かるようになっていたのだ。
結
それでは、新しい物語でまたお会いしましょう。
鈍色の空と堅牢な石畳が織りなす色彩の乏しい景色の中を、一台の馬車が走り抜けて、アデレイド王国の王都にあるブランシャール伯爵家のタウン・ハウスの前で停まった。
馬車の中から出てきたのは、亜麻色の髪を頭の後ろで結わえ、沈鬱な気配を漂わせる水色の瞳を黒いレースで隠した、二十歳の女性。
身に纏うドレスも、靴も、全て宵闇のような黒色だ。
その女性――伯爵令嬢のラシェル・マリュスは、二日ほど前に婚約者のロイク・ブランシャールを喪った報せを聞いたばかりだった。
二カ月前に視察のためここを発った彼は、乗っていた船が大嵐と魔獣の襲撃に遭い、帰らぬ人となった。
後に同じ航路を進んでいた船の乗組員が船の残骸から彼の遺体や遺品を見つけて、王都まで届けてくれたのだ。
タウン・ハウスの扉の前に立っている、初老と思わしき貴婦人が、傘を差してラシェルに歩み寄る。
艶やかな漆黒の黒髪を結い上げた、灰色の瞳をそっと伏せたその貴婦人は、ロイクの母――ブランシャール伯爵夫人。
ブランシャール伯爵夫人は、ラシェルの肩に優しく手をかける。
「雨の中、来てくれてありがとう。急に呼び出して、ごめんなさいね」
「いえ、ブランシャール伯爵夫人に会いたいと思っていましたので、とても嬉しいです」
大切な人を失ったもの同士で一緒に居た方が、ふとした時に感じる会話や表情の温度差に傷つかずに済む。
特に、ロイクの喪失をようやく受け入れ始めた今のラシェルの心は脆くて傷つきやすいため、同じ感情を抱いている者と一緒に静かに過ごしたかった。
「さあ、冷える前に中に入りましょう」
「はい」
ラシェルはブランシャール伯爵夫人に続いて、屋敷の中に入った。
二階へと続く階段の途中に、ブランシャール伯爵家の肖像画が飾られている。
ラシェルは足を止めて、肖像画に描かれたロイクを見つめる。
(もう、会えないなんて……)
ロイクはブランシャール伯爵の次期当主だった。
年齢は二十三歳。容姿端麗で、黒壇のような艶やかな長い黒髪をいつもきっちりと結わえており、切れ長の目は緑色。
顔が整い過ぎているため、一見すると冷たい印象を受ける。そして、寡黙で淡々と話すため一層、冷たく感じられる人だ。
しかし、一緒に過ごしている時にさり気ない優しさが垣間見えるので、ラシェルは彼を好きになった。
(たぶん、私の片想いで終わったのだけど……)
ロイクは優しいが、彼と話していると、自分たちの間に壁があるような気がしてならなかった。
だから、ラシェルはロイクに、お互いを愛称で呼び合うことや、敬語を取り払って話すことなどを提案し、親しくなるきっかけを作った。
ロイクは提案に乗って実践してくれたが、 それでもやはり、彼との間に壁を感じるのだった。
親同士が決めた政略結婚でも恋人のようになれないだろうかと夢見ていたラシェルにとって、彼とはあまり上手くいっていなかった。
(だけど、最期まで私を気遣ってくれていた)
ラシェルがロイクの訃報を聞いた時、懐中時計とその時計にまつわる話を書いた手紙を渡された。
ロイクの遺品を受け取ったブランシャール伯爵夫妻が、これらがロイクからラシェルにあてたものだと知って、ラシェルに手渡してくれたのだ。
懐中時計は、精緻な植物の模様が描かれた金色の本体に、水色の宝石があしらわれている。
ロイクが大切に保管してくれていたからなのか、正確に時を刻んでいる。
手紙によると、この海中時計は途中で立ち寄った港町の蚤の市で見つけた骨董品だ。
魔道具師が〝時戻り〟の魔法を付与した懐中時計らしいのだが、魔法の発動条件を知らせないままこの世を去ったから、誰も使えないらしい。
魔道具に興味があるラシェルのために購入してくれたのだ。
この世界では、誰もが魔法を使うことができるが、時間を操る魔法が使える者は一人もいない。
今までに幾人もの魔法研究者たちが研究をしてきたが、そのような魔法は完成していないのだ。
そのため、人間の持つ力では時間を操ることができないと言われている。
そのような背景もあり、眉唾物な懐中時計だが、ラシェルは肌身離さず持っている。
今も、ドレスのポケットの中に入れて持ち歩いているのだ。
「あの子の遺品を整理していたら、日記が出てきたの。勝手に見るのは悪いと思っていたのだけど、あの子の思い出に浸りたくて読んでみたら、あなたのことがたくさん書いてあって……あなたに知ってもらいたかったのよ」
ロイクの部屋に辿り着くと、ブランシャール伯爵夫人は一冊の日記帳をラシェルに手渡した。
ラシェルは日記帳の表紙を開くと、ぱらり、ぱらりとページを捲っていく。
『今日から、ラシェルをラシェと呼ばせてもらうことになった。ラシェは私を、ロイと呼んでくれる。
ラシェが私をロイと呼んでくれて、とても嬉しかった。ますますラシェを愛おしく思う。』
『ラシェとの会話では敬語を使わないことになった。
うっかり敬語で話してしまった私を見て、笑ってくれたラシェが可愛くて、見惚れていた。』
『外出先で見かけた花がラシェの好きな花だったから、ラシェの顔が思い浮かんだ。
近くの花屋で買って贈ろうとしたが、花屋には売っていなかった。
ラシェに会う口実がなくて残念だ。』
『視察で一人、他国に行くことにした。ラシェが知ったら、どう思うだろうか。』
ラシェルと会った日も、ラシェルと会わなかった日も、ロイクはラシェルについて記していた。
片想いではなかったのだ。
ロイクの心の中には常に、ラシェルがいた。
(ロイは……私を、愛してくれていたのね……)
愛を囁いてくれたことがなかったわけではない。
しかし、ロイクが無表情のままで伝えるものだから、本心なのか測りかねていた。
(もしも時間を巻き戻せるなら――旅立つ前に戻って、引き留めたい)
カチッと、時計の針が動く音がした。
ラシェルは辺りを見回す。壁にかけられている時計に目を留めて、あの時計から聞こえたのかもしれないと思い、視線を日記に戻した。
(ロイに、愛していると伝えたい)
カチッ、カチッ……。
絶え間なく聞こえる音が、次第に大きくなる。
その音が、壁に掛かっている時計よりも近くから聞こえると思ったラシェルは、ドレスのポケットから懐中時計を取り出すと、目を見開いた。
「懐中時計が……光っている……?」
なんと、懐中時計の内側から眩い光が迸ったのだ。
部屋中が照らされて、白く塗りつぶされる。
ラシェルは眩しさに耐えられず、思わず目を瞑った。
◇◇◇
眩しさが収まり、そっと目を見開いたラシェルの目の前に、足首まである長い白銀の髪と紫色の瞳を持つ、ラシェルと同い年くらいの美しい女性がいた。
女性と視線が合うと、女性は安堵したような笑みを浮かべる。
『おお、人の子よ、目を覚ましたか』
「あなたは……?」
『我は時の女神セレストの一部で、その懐中時計に宿っていた。おぬしとおぬしの婚約者の強い思いが合わさって、おぬしを私のもとに導いたのだ』
「時の女神……の一部? なぜ、一部なのですか?」
あまりにも不思議な表現だったため、ラシェルは目を瞬かせた。
『我はセレストが好奇心で分けた魂の一部で、人の子の生活を垣間見たいがために腕の良い魔道具師に頼んで、我の魂の欠片をその懐中時計のなかにおさめてもらったのだ』
「そんなことがあったのですね。ところで、どうして人間の生活を垣間見たかったのですか?」
『そりゃあ、人の子は観ていて面白いからだよ。特に、人の子の恋を眺めるのが好きで、この懐中時計を通して人の子たちの恋を見守れると期待していたのだが、〝時戻り〟の魔法を付与した懐中時計なんて宣伝文句をつけたせいで、力に固執したつまらない人間の手にばかり渡って辟易していたのさ。そこに、おぬしの婚約者が現れて、おぬしの手に渡ったのだよ。ようやく期待していたものを見られると思ったのに、まさかあのようなことが起こるとは……実に不運だった』
セレストは目を伏せた。
懐中時計の中から見たロイクの最期を思い出したようで、声は沈み、少し震えている。
『おぬしたちがお互いに想い合う様子に我の心は揺り動かされたから、一度だけ過去に戻ってやり直しの機会をあげよう。一度しか戻してあげられないから、後悔しないようにするのだぞ?』
「いいのですか?」
『ああ、その代わり、ラブラブな様子を見せつけてくれ』
「ラブラブ……になるといいのですが……自信がないです。それに、ロイはきっと、無表情ですし、私に遠慮しているところがありますし……」
ロイクは初めて出会った頃――十年前からずっと、感情表現が乏しい。
どうにか笑わせようとしてみたが、いつも失敗に終わったのだ。
『ふむ……それでは、恋人のためにこの懐中時計を購入し、自分の身を挺して贈り物を守っていたロイクのいじらしさに感激していたから、おまけをあげよう。ラシェルはロイクの本心が分からなくて困っていたようだから、ロイクの感情が分かるようにする』
「それは、どのようにわかるのでしょうか?」
『なに、すぐにわかるようになるさ』
セレストに聞いてみたところで雑な答えだけ帰ってきた。
そこをもう少し、とラシェルは言いかけたのだが、辺りはまた眩しくなり、白い光に包まれて、なにも見えなくなった。
◇◇◇
意識が浮上したラシェルは、ハッと目を見張った。
いつの間にか、自分の部屋――マリュス伯爵家のタウン・ハウスに戻っていたのだ。
カサリと紙の音がして、手に持っていた新聞を取り落としてしまったことに気づく。
拾って新聞の日付を見ると、二カ月前の日付が書かれていた。
「まって、ロイと最後に言葉を交わした日だわ……」
鏡を見遣ると、ロイクと会うために身だしなみを整えた自分の姿が映っている。
ロイクの瞳の色を意識した、緑色の上品なドレスを着ている。
髪はメイドに編み込みを入れてもらったハーフアップにしている。
「お嬢様、ブランシャール伯爵家のご令息がお見えになりました」
部屋に入ってきたメイドが教えてくれる。
ラシェルはロイクの居場所を聞く前に部屋を飛び出した。
(ロイクは庭園にいるわ。前はなぜ庭園に居るのだろうと思っていたけれど、私が好きな花が咲いていたからかもしれないわね)
日記を読んだからわかる。ロイクはラシェルが喜びそうなことを考えてくれていたのだ。
今からロイクと再会できるのだと思うと、心臓がとくとくと駆け足になる。
再会の感激に視界がじんわりと滲んだ。
ラシェルが目元に力を入れて止めようとしても涙が溢れてしまい、つうっと頬を伝った。
「ロイ! 待っていたわ――」
庭先に出たラシェルは指先で涙を拭い、ロイクを見た。
その時、目の前に現れた、ありえないものを見て目を瞬かせる。
「え……?」
視界の端に、落書きのような何か――絵文字の顔のようなものが現れたのだ。
その顔文字は、目を大きく見開いて【驚いている】顔だった。
目線を動かしてみたが、絵文字の顔はついてこない。それは、ロイクの顔の横にふわんと浮いている。
「ラシェ? どうかした?」
「ロイク、あの……顔の横になにかいるわよ?」
「顔の横に……?」
ロイクは絵文字の顔がある方向に顔を向けたが、すぐにラシェルに向き直った。
「虫……がいたのか? なにも見えなかったから、どこかへ行ったのだろう」
「そ、そう……なのね……」
そんなはずはない。今も自分の目には、見えるのだ。
(もしかして、セレストが言っていた、〝ロイクの感情が分かるようにする〟とは、こういうことなの?)
どうやら自分にしか見えないのかもしれないと悟ったラシェルは、それ以上のことは言わなかった。
今は、ロイクを引き留めることに専念しなければならない。
「泣いていたが……辛いことがあったのか?」
「い、いえ、これは……」
再会できた嬉し涙だと伝えようとして、口ごもる。
そのような事を言っても、信じてもらえないかもしれない。
もしも自分がロイクの立場なら、信じられないような話だ。
「……ロイクが船旅に出ることが、とても恐ろしいの。だから、今度の視察、絶対に行かないで!」
「……!」
ロイクが息をのんだ気配がした。
ラシェルがちらとロイクの顔の横を見ると、ふわんと浮かんでいる絵文字は目を大きく見開いている。
おそらく、【驚いている】顔だ。
「我儘をいっているのはわかっているわ。ロイが投資している商会との重要な視察だとわかっているけど、船旅でもしものことがあったらと思うと、怖くて……。ロイを失いたくないの」
ラシェルの声が震える。
今までロイクにここまで我儘や本心を伝えたことはなかった。
そのことを、今になって気づかされる。
「大好きなロイが死んでしまったら、どうしたらいいかわからないもの!」
「ラシェ……」
ロイクの顔の隣にある絵文字がくるくると表情を変えるため、気になってしまう。
絵文字は頬が赤くなったかと思えば、瞬時に変わって、にこにことした顔でハートマークを浮かばせている。
(ええと……頬が赤くなるのは、きっと【照れている】ということよね。ハートマークを浮かばせているのは、……【好き】ということ?)
ラシェルは戸惑った。
目の前にいるロイクの顔は、いつも通りの無表情なのだ。
それに、ロイクは自分の名前しか言わなかったのに、ここまで感情が変化するのか疑問だ。
絵文字が本当に彼の気持ちを表しているのか、わからない。
「ラシェがそこまで思ってくれていたのなら、私は視察に参加しない。もともと、一年後に控えているラシェとの結婚式の準備に時間を充てたかったから、断ろうか迷っていたところだった」
「えっ、いいの?!」
「視察に行かなくても魔道具で現地の映像を見せてもらえるから、構わない。結婚式は、ラシェとの一生に一度の思い出だから、できる限り一緒に準備をしたい」
ロイクの顔の横にある絵文字が、キッスを飛ばしている顔になった。
(え? この顔って……まさか、【愛している】?)
ラシェルは内心狼狽えながらも、平静を装う。
ロイクの顔と絵文字が一致しないが、話す内容とは一致するように思うと、急に照れくさくなった。
「結婚式のこと、そんなにも気にかけてくれていたのね……」
「ラシェとの行事なのだから、なによりも先に考えている。愛する人と過ごす時間の方が、何倍も大切だ」
ラシェルはロイクの顔の横をちらりと見る。
今度は、両目がハートになっていた。
(ええと……ハートがあるから……これも、【愛している】という意味?)
愛おしく思う感情の中にもレパートリーがあるようだ。
ロイクの顔はやはり無表情なので、ギャップに驚かされるばかりだ。
(言葉と絵文字は、一致しているのね。ロイクは大切に想ってくれていたのに、信じられなくて申し訳ないわ……)
それに、なによりもラシェルのことを一番に考えてくれているロイクのことが、愛おしくてならなかった。
ラシェルはロイクに抱きつく。
ロイクはぴくりと体を揺らしたが、ゆっくりと、ぎこちないながらもラシェルを労わるように、ラシェルを優しく抱きしめ返した。
「ごめんなさい。私、ロイの表情にばかり気をとられて、こんなにも大切に想ってくれていることにきづいていなかった」
「……ラシェは悪くない。私がラシェの立場なら、感情のこもっていない声と顔で何を言われても信じられなかっただろう。だから変わろうとしたのだが、幼い頃からの癖が抜けてくれなかった」
ロイクは初めて、彼が感情表現に乏しい理由を教えてくれた。
ロイクはラシェルに会う二年前、懐いていた剣術の先生に誘拐されたことがあった。
幸にも使用人がすぐに気づき、ブランシャール伯爵夫妻やブランシャール伯爵家の私設騎士団の騎士たちに伝えてくれたおかげですぐに助け出された。
しかし、信じていた相手からの裏切りに、ロイクの心はひどく傷ついた。
そんなロイクに、当時生きていた祖父が、「隙があるとすぐに狙われるから、感情を隠しなさい」と助言したのだ。
それ以来、ロイクは感情を上手く消すようになったが、逆に感情を表に出すことができなくなってしまった。
ラシェルは、感情を消そうとするほど傷ついたロイクに同情した。
「ラシェルをたまらなく愛しているのは本当なんだ。行動で示すと、伝わるだろうか?」
「たぶん……そうだとおもうわ」
ラシェルはそっと、ロイクの顔の横を盗み見る。
絵文字はまた、ラシェルにキッスする顔になっていた。
「本当は結婚式まで我慢していたのだが、ラシェに気持ちをわかってもらうためにも、我慢を止めよう」
「えっ、我慢って――んっ」
ロイクはラシェルの頬に手を添えると、唇をそっと塞いできた。
ふにゅと唇に触れた柔らかな熱が、ラシェルの唇に移る。
『ああ、よかった。めでたし、めでたし』
ラシェルは、どこからともなくセレストの声が聞こえてきたような気がした。
その後、ラシェルはロイクに訴えかけて、彼の投資先の人たちが嵐に遭わない日に出発することに成功した。
おかげで、その商談は被害に遭わず、今も健在だ。
ラシェルとロイクは二人で結婚式の準備をして過ごし、結婚後も仲睦まじく過ごした。
ロイクは言葉や行動でラシェルへの愛を伝えようとすることになったため、ラシェルは毎日ロイクにたくさん愛されて、最初は戸惑っていたが次第に慣れてしまう。
そうして一緒に過ごしていると、ロイクの顔の横にあった絵文字は、ある日突然消えてしまった。
しかし、その顔文字が無くても、ラシェルはロイクの気持ちが分かるようになっていたのだ。
結
それでは、新しい物語でまたお会いしましょう。